島墘 II 乽儊僞儃儕僢僋徢岓孮偲怘昳偺婡擻惈乿
島巘丂偍拑偺悈彈巕戝妛惗妶娐嫬僙儞僞亅
嫵庼丂嬤摗丂榓梇愭惗
徍榓30擭戙丄懢偭偰偄傞偺偼寬峃桪椙帣偺徹偩偭偨丅崱偼懢偭偰偄傞偙偲偑條乆側昦婥偺梫場偵側偭偰偍傝丄偦傟傜偺昦婥偼堦恖偺恖偺拞偱摨帪偵婲偙偭偰偄傞丅昦婥偼乽僔儞僪儘乕儉倃乿乽巰偺巐廳憈乿乽撪憻帀朾徢岓孮乿偲傕尵偆偑丄堦斒偵偼乽儊僞儃儕僢僋徢岓孮乿偲屇偽傟偰偄傞丅
帀朾嵶朎偺戙幱堎忢偐傜傾僨傿億僒僀僩僇僀儞偑拞惈帀朾丒寣埑丒寣摐偵埆偄塭嬁傪媦傏偟偰偄傞丅
怘廗姷偐傜偺塭嬁偑儊僞儃儕僢僋僔儞僪儘亅儉傪婲偙偟丄摦柆峝壔偵敪揥偟偰偄偔丅尵偄姺偊傞偲丄怘廗姷傪曄偊傟偽昦婥偵側傜側偄偺偱偁傞丅摦柆峝壔偺婋尟場巕偱偁傞崅帀寣徢丒摐擜昦丒旍枮丒崅寣埑偼娗棟丒夵慞偱偒傞傕偺側偺偱偁傞丅
寣娗暻偵偱偒偨僾儔亅僋偑攋偗偰彎傪廋暅偡傞偨傔偵寣愷偑偱偒丄峓嵡偼偦偺寣愷偑戝偒偔側偭偨応崌偵偍偒傞丅擼峓嵡傕偦偆偱偁傞丅懱撪偺帀朾偵偼僐儗僗僥儘亅儖丒拞惈帀朾丒儕儞帀幙丒梀棧帀朾巁偑偁傝丄慡偰懱偵昁梫側傕偺偩偑丄懡偔偁傝偡偓傞偲懱偵埆塭嬁傪媦傏偡丅
寣拞偺憤僐儗僗僥儘亅儖抣220噐/dl偲寛傔偰偄傞偺偼丄姤摦柆幘姵敪徢棪婋尟搙偑塃尐忋偑傝偵側傞嫬栚偺抣偩偐傜偱偁傞丅
擔杮摦柆峝壔妛夛偵偍偄偰乽崅帀寣徢乿夵傔乽帀幙堎忢徢乿偵柤徧傪曄偊傞偙偲偑寛傑偭偨乮悽奅婎弨偵崌傢偣丄掅HDL僐儗僗僥儘乕儖乮埲壓HDL乯寣徢偼擖傟側偄乯丅傑偨憤僐儗僗僥儘乕儖抣偱偼側偔丄LDL丒HDL偱敾掕婎弨抣偵偟傛偆偲帋傒偰偄傞丅
帀幙堎忢徢偺帯椕偵偼1.怘帠椕朄2.栻暔椕朄3.寣燋岎姺側偳偑偁傞丅栻暔椕朄偱敪徢棪傪壓偘傞偙偲偼偱偒傞偑30乣40亾偵偡偓側偄丅傑偢怘帠椕朄偑戝愗偱偁傞丅
僄僱儖僊乕偺塰梴慺暿愛庢峔惉斾偱偺帀幙偺愛庢忬嫷偼1985擭傛傝24乣26亾偱偁傝丄摨帪婜丄帀朾幘姵傕墶偽偄偲側偭偰偄傞丅備偊偵帀朾偺愛傝曽偑廳梫偵側偭偰偔傞丅
帀幙堎忢徢偺怘帠椕朄偼丗乮侾乯帀朾僄僱儖僊乕斾25亾埲壓乮俀乯懡壙晄朞榓帀朾巁丗堦壙晄朞榓帀朾巁丗朞榓帀朾巁傪俁丗係丗俁丄乮俁乯n-3宯帀朾巁丗n-6宯帀朾巁傪侾丗係丄乮係乯僐儗僥儘乕儖300mg埲壓偵側偭偰偄傞丅偙偺晄朞榓帀朾巁偱偁傞儕僲乕儖巁丄僆儗僀儞巁傪愛庢偡傞偙偲偵傛傝寣拞僐儗僗僥儘乕儖抣偑掅壓偡傞丅傑偨EPA丄DHA偵偼拞惈帀朾偺惗惉傪朩偘傞岠壥偑偁傞丅摨偠帀朾偱傕帀朾巁偺堘偄偱怱憻昦偵滊傝擄偔側傞丅
嶐崱拲栚偡傋偒傕偺偵拞嵔帀朾巁丒怉暔僗僥儘乕儖偑偁傞丅怉暔僗僥儘乕儖偼僐儗僗僥儘乕儖偲峔憿偑帡偰偄傞偨傔丄彫挵偐傜堦扷偼媧廂偝傟偰傕丄曄壔偡傞偙偲偵傛傝攔弌偝傟傞偨傔丄帀幙偲偟偰媧廂偝傟側偄偺偱偁傞丅
摦柆峝壔偼埆嬍僐儗僗僥儘乕儖乮LDL乯偑杮摉偺埆嬍僐儗僗僥儘乕儖乮巁壔LDL乯偵曄壔偟偰偍偒傞丅峈巁壔暔幙偼偦偺巁壔傪梷惂偱偒丄價僞儈儞俤丄價僞儈儞俠丄兝僇儘僥儞丄億儕僼僃僲乕儖偑偦傟偵偁偨傞丅億儕僼僃僲乕儖偼傎偲傫偳偺栰嵷傗壥暔偵娷傑傟偰偍傝丄椺偊偽椢拑丄儗儌儞丄愒儚僀儞丄僠儑僐儗乕僩側偳偵懡偔娷傑傟傞丅怘帠偱堦弿偵愛傞偙偲偵傛傝挵娗偺帀朾媧廂傪梷惂偡傞丅
杮棃偼僄僱儖僊乕偺挋憼屔偱偁傞拞惈帀朾偑憹偊傞偲傛偔側偄偺偼丄摦柆峝壔偵側傝傗偡偄娐嫬偵側傞偐傜偱偁傞丅偦偺娐嫬偼丄儗儉僫儞僩乮拞惈帀朾傪懡偔娷傓儕億抈敀乯偑憹偊丄仜摦柆峝壔傪婲偙偟傗偡偔側傞仜LDL偑彫棻巕壔偟偰曄惈偟傗偡偔側傞仜HDL偺検偑掅壓偡傞仜寣愷偑偱偒傗偡偔側傞側偳偱偁傞丅
拞嵔帀朾巁値-8乣値-10偼悈偵恊榓惈偑偁傝乮悈偵梟偗傞乯懱撪偵拁愊偝傟側偄偱娞憻傪宱偰僄僱儖僊乕偲偟偰岠棪傛偔暘夝偝傟傞丅怘帠娗棟壓偵偍偄偰拞嵔帀朾巁傪挿婜愛庢偡傞偙偲偱懱廳丒懱帀朾検丒暊晹帀朾柺愊(旂壓丒撪憻)偑尭彮偟偨椺偑偁傞丅
傾儖僼傽-儕僲儗僀儞巁乮値-3宯帀朾巁丄懱撪偱EPA丄DHA偵曄姺偝傟傞乯偵偼寣埑梷惂岠壥偑偁傞丅偦傟偼寣娗奼挘暔幙乮僾儘僗僞僒僀僋儕儞丒堦巁壔拏慺丒僽儔僕僉僯儞乯傪憹壛偝偣傞椡偑偁傞偐傜偱丄奀奜偱偼愛庢偵傛傞寣埑掅壓曬崘傕偁偑偭偰偄傞丅
儊僞儃儕僢僋徢岓孮梊杊丒帯椕偵偼丄怘帠椕朄傗丄偙偺傛偆側條乆側怘昳傪偄偐偵棙梡偡傞偐傕戝愗偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅
乮暥愑丂抧妶丂倀.俿乯
![]()
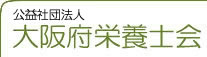
 儁乕僕僩僢僾傊
儁乕僕僩僢僾傊